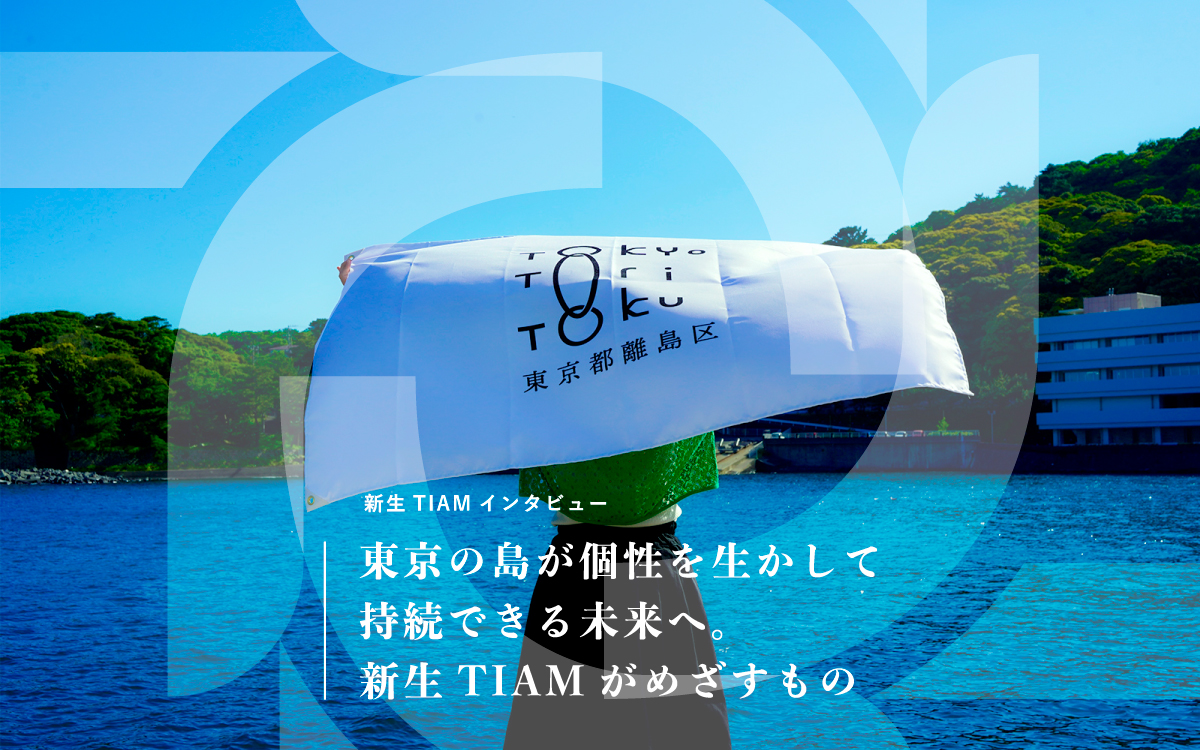
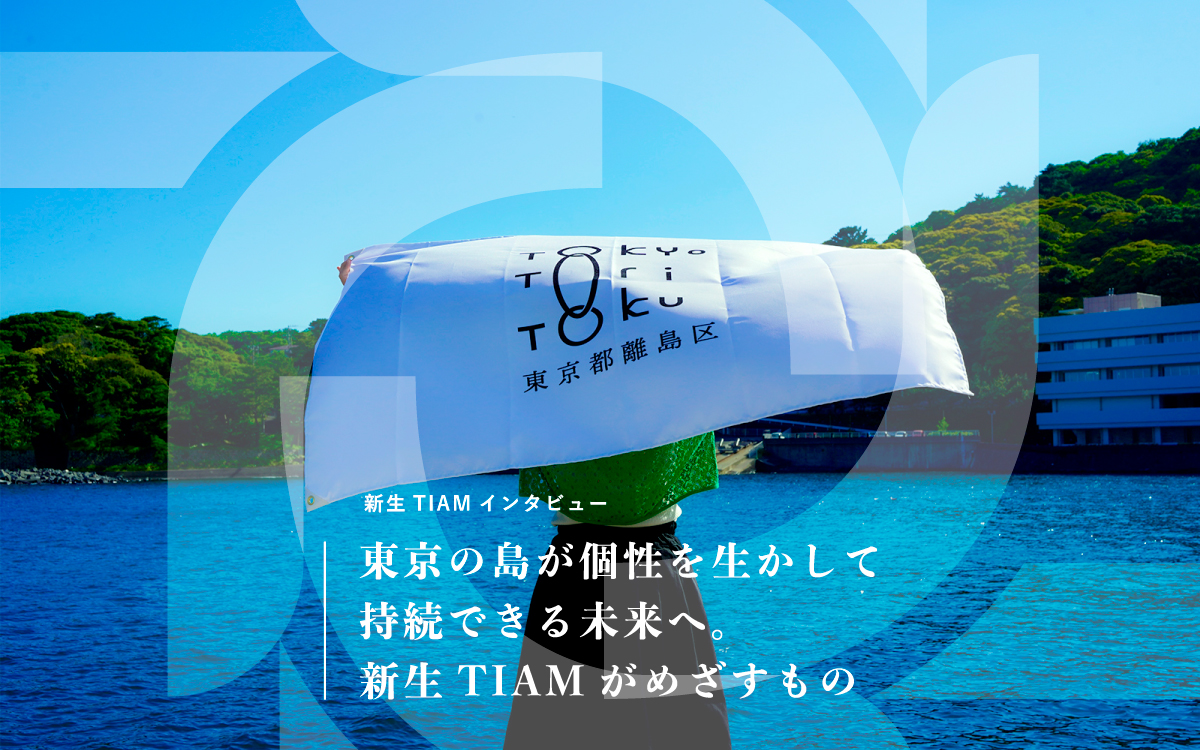
東京の島が個性を生かして持続できる未来へ。新生TIAMがめざすもの
株式会社TIAMは2025年4月より新たな経営体制へと移行しました。この転換期を機に、あらためてTIAMの存在意義を問い直し、事業活動の本質を再確認することで、私たちが抱いているミッションの再定義と将来ビジョンの明確化に取り組んでいます。そこで、より客観的な視点を得るべく、新島を拠点に活動されている一般社団法人 新島OIGIEの宮川由美さんにインタビュー取材をお願いしました。
新生TIAMインタビュー
「東京諸島の“かけがえのない宝物”を未来へつないでいきたい」
その強い思いを掲げ、2022年1月に設立された株式会社TIAM。都市と島、旅人と住民、人と自然、それぞれの新しい関わり方を提案し、3年にわたり都内や島々で多彩な活動を続けてきました。
そんなTIAMが今年4月、創立メンバーの一人だった伊藤奨さんが社を離れ、新たな体制がスタートしました。TIAMでこれまでに築き上げてきたもの、そしてこれから実現したいこととは? CEOの千葉努さん、チーフディレクターの空佐和さんに、じっくりとお話を伺いました。
「24区目の東京」に込めた世界の広がり
新代表となった千葉努さんは2010年、奥様の故郷である伊豆大島に家族で移住。デザイナーとして夫婦でデザインオフィスを営みながら、コミュニティスペースの運営やフリーペーパーの発行、情報サイトの編集制作、店舗デザインなど、地域に根ざした活動を展開してきました。そんな彼のもとに2021年のある日、三宅島でゲストハウスを営む“いと~まん”こと伊藤奨さんが訪ねてきたことが、TIAMのはじまりでした。
「当時はコロナ禍のまっただなか。宿が休業状態に追い込まれたいと~まんが、『いつもは会えない島の人に会いにいこう』と東京諸島の島々を訪ね歩いていたんです。彼とはイベントなどで一緒になることはありましたが、じっくり話したのは初めてだったと思います。
当時、自分のなかで『東京都離島区』というキーワードが漠然とあって。東京といえば首都、首都といえば23区というイメージがありますが、東京は都会だけじゃない。東京の島にも23区に負けない魅力があることを伝えたいという思いが強くなっていたんです。港区の竹芝桟橋から離島行きの船が出ているんだから、港区の次は離島区じゃない?という連想から出てきた言葉でした。
そのころ大島では若くてアクティブな人たちが宿を始めたり一次産業に着手したりと、個性を生かした事業を始められる動きがあちこちで起こりはじめていた時期で。そういう方をしっかり紹介して広く発信することで、『島って面白いね』と感じる人が増えるんじゃないか。そういう思いが募っていたんですよね。

大島の情報サイト「伊豆大島ナビ」内に「東京都離島区」という特集記事を設けていた頃の告知用につくったポスター
一方で、伊藤は東京の島々を転々としながら生きてきた人。島に育てられたという思いが強く、この場所をちゃんと愛して次の世代に引き継いでいくんだという使命感があるように感じました。そういうなかで『東京都離島区』という言葉が彼の中でも響いたようで、『メディアが呼び水となって、外の人が島に関わってくれるような流れをつくりたい。一緒にやりませんか?』と誘われたことが、TIAM結成につながりました」
取材だけで終わらない、クリエイティブなつながり
意気投合した二人は2021年、東京諸島の未来を考えるWebメディア『東京都離島区』をローンチ。それぞれが得意分野を生かして記事を制作し、新しいスタイルの情報発信が話題となりました。その後、モニターツアーやワークショップの開催、都内イベントでの企画展示など、自治体や企業との連携事業を展開。2023年にオープンした伊豆大島のコワーキングスペース『Izu-Oshima Co-Working Lab WELAGO』では、都内の企業とともに施設の共同運営を開始。TIAMは現地における施設管理・運営を担当、地域を横断する活動に注目が集まりました。

Izu-Oshima Co-Working Lab WELAGO外観
「TIAMに相談すれば何か新しいことができるんじゃないか?と感じてもらえたことは、幸運だったと思います。僕たちが大切にしているのは、単なる取材に終わらない関係の構築。取材から新たな発想が生まれたり、新しい企画につながったりするような、クリエイティブな機会になればいいなと思っています。表からは見えない思いを聞けるのは嬉しいですし、相手の思いを受け止めたうえで自分にできることはないか?と考えるのも面白いです。編集者的視点でより広くモノゴトを捉えていくイメージでしょうか。

TIAMメンバーと新島の羽伏浦海岸にて
伊藤が旗振り役としてフロントに立ち、僕がクリエイティブディレクターとして裏方を担うという、互いの得意分野を生かした3年間でした。伊藤から『次の夢にチャレンジしたい』と言われたときは、正直、驚きました。けれど結成から時間が経ち、1年前から空という新しい仲間も増え、組織として変わりつつあったことも事実。伊藤を送り出すとともに、自分たちにしかできないやり方で道を切り開いていきたいと思っています」
地球の営みを全身で味わう島の暮らし
もうひとりのメンバーである空さんは、1年前よりTIAMに参画。初めて離島と出会ったのは大学1年生のときで、参加したボランティアプログラムで三宅島に滞在した際、伊藤さんと出会ったことが縁となりました。

地球の息吹を感じる三宅島での滞在の一コマ
「三宅島で離島の暮らしって面白いなって興味が湧いて、その後、島根県隠岐島の海士町でアルバイトしながら住める『離島ワーホリ』というプログラムがあることを知り、大学2年のときに参加しました。1カ月の滞在予定だったんですが、滞在中にコロナ禍が始まり『今はまだ東京に戻らないほうがいいんじゃない?』と滞在を延長させてもらうことができ、結局3か月半ほど島で暮らすことになったんです。
もともと“人と人がつながることで化学反応が起きて大きなパワーになる“という瞬間が好きで、場づくりを仕事にできたらいいなと思っていたんです。そういう意味で、海士町での経験はすごく大きかったですね。旅行では見えない地域のいい面や悪い面が見えたと同時に、島のなかで団結しているからピンチのときに立ち上がる力が湧くんだとわかって、島への興味がいっそう強くなりました」
大学卒業後はオンラインをベースとしたコミュニティを支援する仕事で経験を積んだ後、TIAMに転職。大島に移住し、東京都離島区のライターとして活動しながら、WELAGOのコミュニティマネージャーとして場づくりへのチャレンジをスタートしました。
「大島での暮らしは、いい意味でイメージと全然違っていましたね。なにより感じるのは、一次産業の人とつながる楽しさ。内地にいた頃は、スーパーに並んでいる食材を誰がつくっているのかわからなかったけれど、島ではつくる人の顔が見えます。
養豚をされている人はこういう生活リズムで豚を育てているんだとか、この人とこの人がつながって新しい商品が生まれたんだとか、取材や生活のなかで得る気づきや発見にパワーをいただくことも多いです。人間関係も断然面白い!WELAGOでも来てくださった方とはどうにかしてつながりたくて、隙あらば声をかけています(笑)。
もうひとつ大島で気づいたのは、社会課題をいち早く体験できること。人口が減るとこういう影響が出るんだ、環境破壊が起きるとこんな風になるんだ、と社会問題も初めて感覚として理解できたというか。そういう意味で、島って最先端。すごく面白い場所だと思います」
島の個性が集うアメーバ型ネットワークへ
千葉さんと空さんの2人体制で、新たなスタートを切った新生TIAM。これから目指す道について伺うと、「商店街のようなつながり」と言う言葉が返ってきました。
「これまでは東京諸島という一つの旗のもとに集まり団結するようなイメージでしたが、これからは島それぞれが個性を生かし、高めあえるようなつながりの機会をつくりたいなと思っています。というのも僕の原体験として、宇都宮でまちづくりをしていた友人の存在があって。建築家だった彼はシャッター商店街を復活させようと宅建士の資格を取り、商店街の1角をリノベーションして設計事務所と不動産業を始めました。

宇都宮の友人ことビルススタジオの塩田さん(右から2番目)と日光珈琲代表の風間さん(左)を訪ねて栃木へ
そして友人は『この場所に、この人がいたらもっと面白くなるだろうな』という人たちをヘッドハンティングして、商店街に呼びこんでいたんです。ちょうど今の波浮港みたいに個性的な小さなお店が少しずつ増えて、町がどんどん変わっていきました。そんな友人が仕掛けた”面白い人を集めることで面白い場所になる”という動きを目の当たりにして、自分がやりたいのはこういうことなんじゃないかと、漠然と思ったんですよね。
これからのTIAMは、島々がそれぞれに主体性を持って面白いことをしていて、僕たちはそこにお邪魔してお話を聞いて、記事にしたり、MeetUpイベントのような企画で互いに発表しあう場をつくったりして高め合うお手伝いをしたい。アメーバ的にゆるやかにつながりながら、生き物のように新陳代謝をくり返していく。そんな活動を通じて、好奇心を刺激するようなエリアづくりに貢献していけたらいいなと思っています」
もうひとつのキーワードはWELAGOの共同運営者である株式会社フロンティアコンサルティングが中心となって掲げている「ネイチャーポジティブ」。いろいろな価値観が複雑に絡み合う世界で今後どう生きていけばいいのか、予測不可能な時代の道しるべとなるのは“地球規模のまなざし”だと千葉さんはいいます。
「これからは自然の生態系にヒントを得て自分たちの活動に活かすような、より広い視点でものごとを捉えて考えていくことが重要な社会になっていくと感じています。大島と椿の関係もそうですが、人と自然が深く関わって今の暮らしがある。それをより強く深く感じることができるのが、離島という場所ではないでしょうか。

新島で塩づくりを行っている塩職人斉木さんの取り組みをまとめた展示パネル
最近では大島で椿の備長炭の製造を始めた人や、特定外来生物であるキョンのジビエ化に取り組む人が現われていますし、新島では海塩をつくり始めた人に若者が集まっています。彼らの話を聞くと、思考スケールの大きさに驚かされますね。仕事として取り組んではいるけれど、その奥には森を再生する、海を蘇らせるという地球規模のまなざしがある。それは都会では持ちづらい視点なので、彼らの目線をちゃんと表現して、伝えることで、気づきを与えられるメディアになりたいです」
今後はメディアとしての発信力を高めていくとともに、WELAGOではイベントやワークショップなどさまざまな企画が予定されている。この先の構想としてカフェスペースの立ち上げなどもアイデアとしてあがっており、豊かなコミュニティが生まれ、育つ、より親しみやすい場所にしていきたいと千葉さん。さらに年内には新事業として、東京都離島区のブランドやコミュニティを育んでいくためのリアル拠点の立ち上げも計画中。新たなチャレンジをはじめるTIAMの今後に注目です。
Let's Share
この記事をシェアするRelated articles
関連記事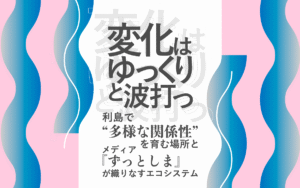
変化はゆっくりと波打つ—利島で“多様な関係性”を育む場所とメディア『ずっとしま』が織りなすエコシステム
波の間を縫うように、ゆっくりと芽吹く変化。利島では「関係をつくる場所」とコミュニティ型ポータルサイト『ずっとしま』が、日々の小さな気づきを合図に共感を集め、挑戦・・・
2025/10/16

アイランデクスさんと行く!「人生に離島を」的ドキドキ離島引越し体験記
離島への引越しを計画したいけど、なかなか住まいが見つからない。住まいが見つかっても、離島への引越しをお願いできる業者がわからない。船での輸送の際に、荷物が壊れな・・・
2024/04/09







