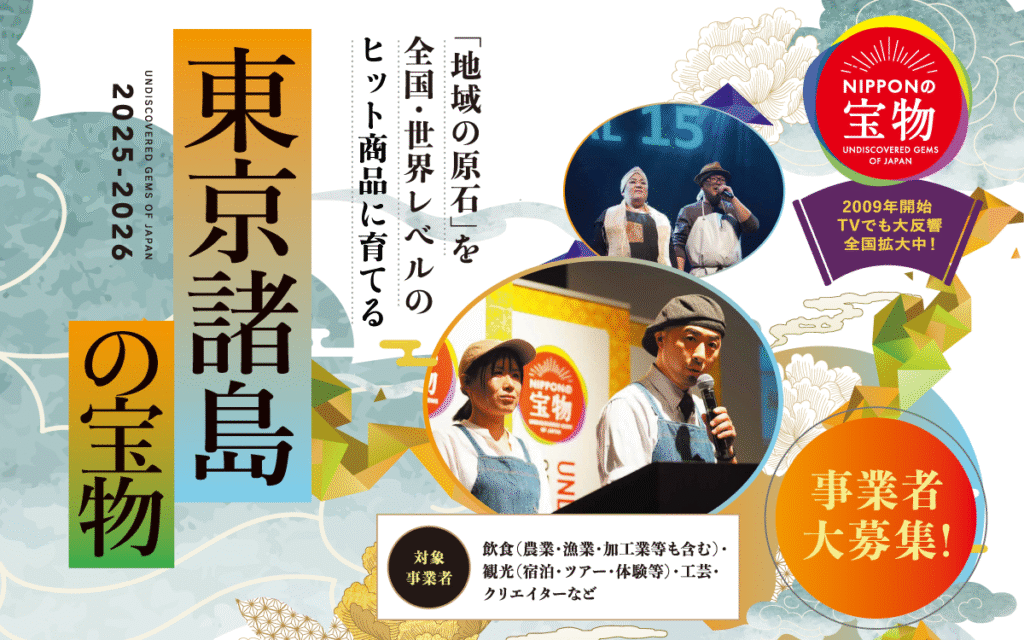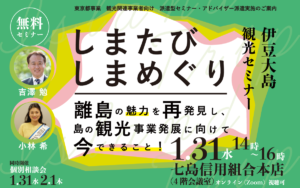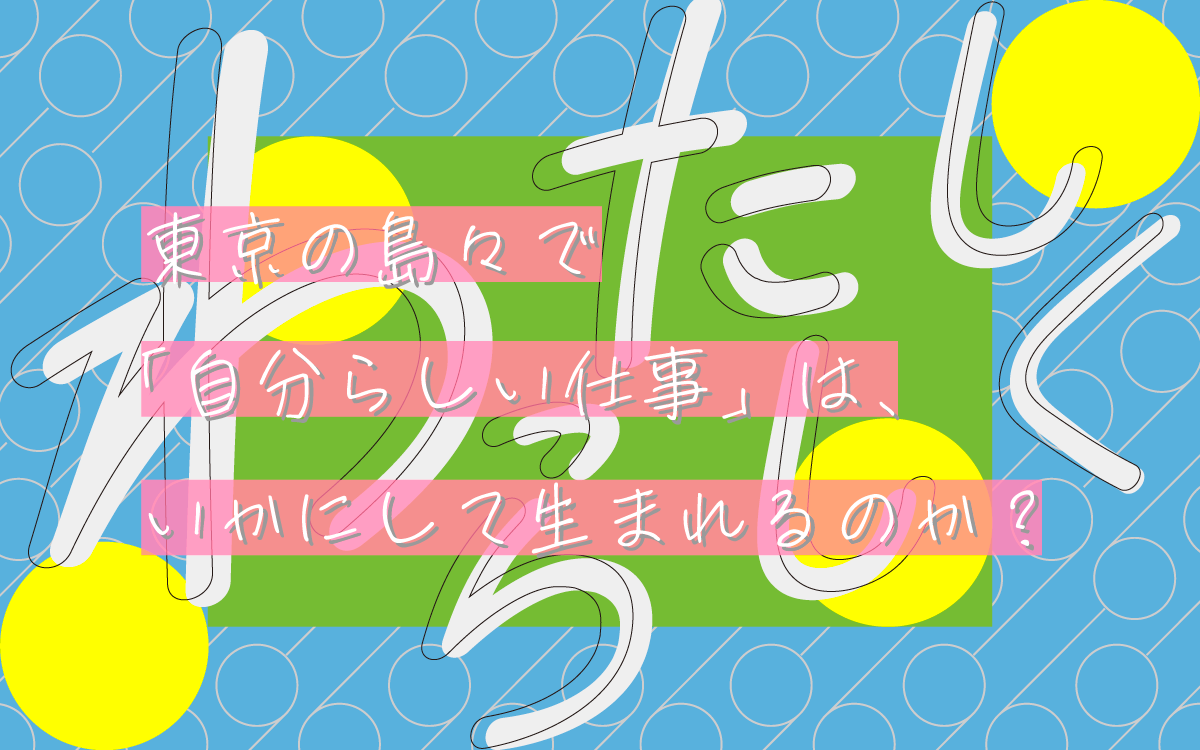
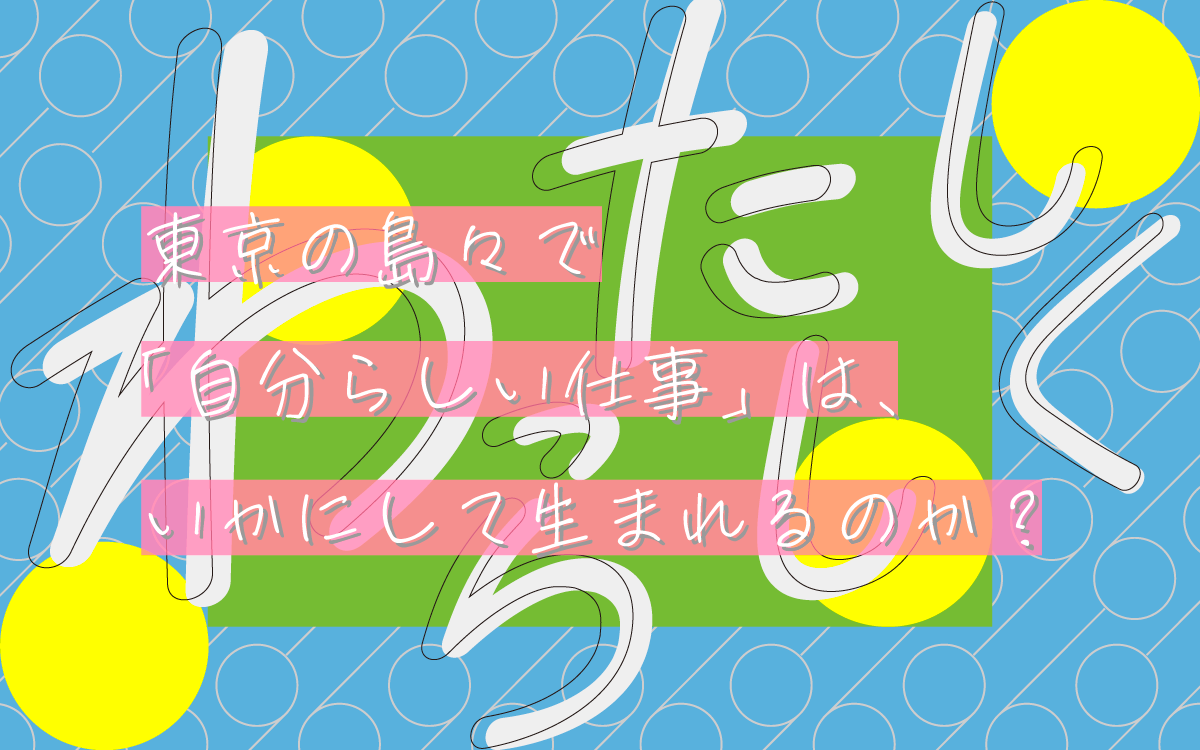
東京の島々で「自分らしい仕事」は、いかにして生まれるのか?ーライフプロジェクトという“起点”
2025/09/17
オンラインセミナー後記
2025年9月5日、伊豆大島のコワーキングスペース WELAGO から、創業・事業承継をテーマにしたオンラインセミナー『しまと わたし らしく くらす』を配信しました。本セミナーは東京都商工会連合会の主催によるもので、ご参加くださった皆様、ご登壇いただいたゲストの皆様、そしてご協力いただいた関係者の皆様に心より感謝申し上げます。皆様から寄せられた視点や質問は、島の未来をさらに具体的に描き出す貴重なヒントとなりました。
今回は、このセミナーで私(WEBメディア「東京都離島区」編集長・千葉)が語った内容を基に、そのエッセンスを振り返ります。
「こうしたい」からはじまる“ライフプロジェクト”が社会を変える
私たちが「東京都離島区」における取材を通じて出会ってきた多くの事業や活動は、誰かに求められたからではなく、「こうしたい」という内発的な想いから生まれる小さな実践が起点となっています。私たちはこの一歩を、地域コミュニティの文脈で「ライフプロジェクト」と呼んでいます。東京の島々における事業承継や創業をテーマにした今回のオンラインセミナーでは、離島で事業を行ううえでの重要な視点として、この「ライフプロジェクト」——すなわち自分にとって意味を見いだせる仕事や活動かどうかという問いを設定しました。

ライフプロジェクトが周囲に共有され、仲間や地域のさまざまな組織・制度と結びつくことで、活動は着実に広がっていきます。やがて単発の取り組みが、新しい関係性の構築やサービス、運営の仕組みへと育ち、既存の枠組みでは届かなかったニーズを満たし始めます。そして、個人の内発性から始まった実践が、人・組織・制度との協働を通じて、これまでの当たり前の前提や仕組みを問い直し、新しい関係性の結び方や運営のルールを生み出していく過程をソーシャルイノベーションと捉えています。その途上で相互扶助に資する信頼といった関係財が育まれ、「わたしを生きる」状態が広がります。
「私」が起点だからこそ続けられる。そして、さまざまな価値観を持つ人々との交差を通じて新たな発見や価値観の揺さぶりが起こる。そんな営みを繰り返しながら、新たな価値の創出や枠組みの更新へとつながるソーシャルイノベーションへと発展していくと思うのです。
過疎化や産業の衰退、気候変動やパンデミックなど、先行きが見えない時代だからこそ、個々人の内発性から始まるライフプロジェクトに、社会のあり方を変えていく大きな可能性を強く感じています。
そんな視点をベースに、今回は4つの事例をご紹介しました。
途絶えかけた歴史を「今」につなぐ二つの挑戦
事例① 伊豆大島「椿の備長炭」/株式会社東京備長・平井雄之さん
伊豆大島で椿の備長炭を製造する株式会社東京備長・平井雄之さんは、椿の花から実、油、木、炭、灰へと循環させる島の知恵に魅了され、高知県室戸市の窯元での修行を経て、2025年に自らの窯を完成させました。椿炭はかつて年貢にもなる特産品でしたが、燃料革命により産業は衰退。平井さんは炭焼きを、森と海の循環を人の手で再起動する営みとして位置づけます。過密化した森林は土砂を海へ届けにくくし、砂浜や生態系に影響を与えるため、適切に木を伐採し、炭へと付加価値化することは、環境面でも文化面でも「循環を取り戻す」行為なのだと教えてくれます。

事例② 新島「しおさいの塩」/斉木佑介さん
新島で「しおさいの塩」を手がける斉木佑介さんは、成り行きで移住し、飲食店の承継後のコロナ禍を機に「食」と真剣に向き合い始めました。やがて塩の本質的な価値に気づき、江戸時代に途絶えていた新島の製塩技術を再生することを決意。山口県長門市で技術を学び、新島特有のコーガ石を活用した製法で塩づくりを再開しました。新島の豊かな自然と共にある美しい海とつながる体験、それは単なる食料品ではなく、土地の物語をもう一度編み直す取り組みなのです。
空き家を「新しい人の集う場所」へ変える実践
事例③ 伊豆大島「島ぐらしカフェ chigoohagoo(ちぐはぐ)」/浅沼みやさん × 長瀬なつみさん
伊豆大島の「島ぐらしカフェ chigoohagoo(ちぐはぐ)」は、大島出身の浅沼みやさんと長野出身の長瀬なつみさんが、空き家を生かして宿とカフェを共同運営しています。議論と試行錯誤を重ねてたどり着いたコンセプトは「女性が自分らしさを取り戻せる場所」。その意図は運営においても具体化されています。朝は島のエネルギーを感じてもらえる時間に、夜は帰路につく前にリラックスできる時間に——カフェはあえて朝と夜だけ営業。宿は女性優先・1日2組限定とし、動線やアメニティにも細やかな配慮を施しています。二人は「相手の夢を叶えることが自分の夢も叶える」という姿勢で、効率ではなく“信頼”を積み重ねながら場を育んでいます。
※現在は差木地で新たにカフェを営むお二人ですが、本セミナーでは移住直後の岡田地区での創業事例をご紹介しました。
事例④ 伊豆大島・波浮港「青とサイダー/高林商店/波浮港醸造」/吉本浩二さん
波浮港の吉本浩二さんは、幼い頃に通った駄菓子屋の建物を引き継いで「青とサイダー」を開業しましたが、台風で屋根が飛ぶ大きな被害に遭いました。仲間の支えとクラウドファンディングで再建し、被災した隣の「高林商店」も事業承継。さらに現在は「波浮港醸造」を立ち上げ、クラフトビールの醸造に挑戦しています。吉本さんが繰り返し語るのは「波浮の灯りを絶やさない」こと。宿や商店は建物だけで完成せず、笑い声と出会いによって“場”になるのだと、実践で示しています。

地域に根づきひろがる営みの3つの鍵
以上の実践から見えてきた、地域に根づき広がる営みに共通する要点を3つに絞って整理します。
- 矛盾のない仕事であること(経済合理性だけに寄りかからず、自然資本・文化資本・社会関係資本を束ね直します)。
- 起点の明確さ(「なぜ自分がやるのか」を自分の言葉で定義し、行動に落とし込みます)。
- 接続の設計(人と制度、内と外、歴史と現在をつなぎ、取り組みを持続・拡張させます)。
わたしたちは、島と人とをつなぐ「うつわ」を目指します
私たち「東京都離島区」は物語を紡ぐメディアとして、そして Izu-Oshima Co-Working Lab WELAGO は人が交わる“うつわ”として、この起点と接続を支える存在でありたいと考えています。小さく始めて、続けること。続けながら、誰かと交差すること。その交差点で、思いがけないイノベーションが生まれます。そんな動きが東京諸島のそれぞれのローカルで継続的かつ発展的に起こるような場所であってほしいですし、そんな流れをつくっていきたいと考えています。意味のある一歩を、ここから一緒に形にしていきましょう。

最後に、私たちTIAMが取り組む、“ライフプロジェクトの「交差点」”となる直近の事業を2つご紹介します。是非、チェックしてみてください。
お互いが幸せになれる、事業承継・創業を考える『自分らしい島との関わりを見つける 島しょ交流会 in 三宅島』参加者募集!
東京の島々での“創業・事業承継”をリアルに学び、地域とつながるための交流プログラム『COMMONS Meeting 島しょ交流会』を、今年は三宅島で開催します!日程は2025年11月22日(土)・23日(日)の2日間です。
にっぽんの宝物「東京諸島の宝物」セミナー&グランプリ 参加者募集【2025】
にっぽんの宝物「東京諸島の宝物」セミナー&グランプリ 参加者募集。東京諸島で培った“わたしの仕事”を全国・世界へ。商品磨き×コラボ開発×販路接続を短期で加速する実践プログラム「宝物セミナー&グランプリ」を開催します。参加無料。会場・オンラインのハイブリッド開催で、まずはセミナーからどうぞ。
Let's Share
この記事をシェアするRelated articles
関連記事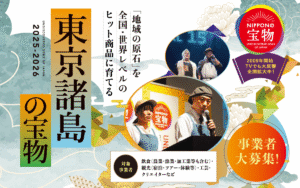
にっぽんの宝物「東京諸島の宝物」セミナー&グランプリ 参加者募集【2025】
にっぽんの宝物「東京諸島の宝物」セミナー&グランプリ 参加者募集。東京諸島で培った“わたしの仕事”を全国・世界へ。商品磨き×コラボ開発×販路開拓を短期で加速する・・・
2025/09/08

【第4回竹芝みなとフェスタに出店】東京諸島の誇りにふれる「離島区商店」がはじまります。
東京諸島の誇りにふれる「離島区商店」が3月15日(金)・16日(土)の2日間にわたって開催される第4回竹芝みなとフェスタに出店します。ぜひ竹芝にお越しください。・・・
2024/03/03