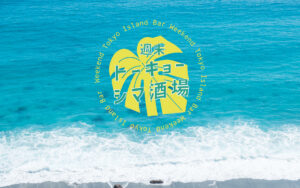伊豆大島で「ずっとしま」のこれからを考える—利島村のみなさんとの大島視察レポート
2025/11/20
「利島村ずっとしま計画2030」から生まれた、大島行きの理由
利島村では、人口約300人の小さな島のこれからを見据えた「利島村ずっとしま計画2030」が策定され、「ふらっと、もっと、ほっと ずっとしま」を将来ビジョンに掲げています。訪れる人、関わる人、暮らす人が「としまとずっと」でありつづけるための移住・定住計画であり、その中核として位置づけられているのが、複合型サテライトオフィスとコミュニティ型ポータルサイト『ずっとしま』です。

建設が進む複合型サテライトオフィス
サテライトオフィスは、「遊ぶ・学ぶ・働く・育む・つながる」をひとつ屋根の下で束ね、子どもからお年寄り、島内外の人が交わるコミュニティ拠点として構想が進んでいます。
一方で、子育て世帯や小中学生へのアンケートからは、「雨の日でも全身を動かして遊べる場所」や「集中して学べるスペース」への強いニーズも見えてきました。こうした声を踏まえ、室内遊び場や学習スペース、コワーキング、カフェ機能などをどのように一体的に設計していくかが、利島の移住・定住の鍵を握っています。
さらに、拠点を単なる「施設」ではなく、島内外の〈わたし〉の「やりたい」を耕し、行動と関係性、そして地域のウェルビーイング(よく生きるあり方)につなげていく“ウェルビーイングラボ”として位置づける構想も、プロジェクトの中で育まれてきました。
今回の伊豆大島視察は、そうした構想をより「手触りのある未来像」にしていくためのフィールドワーク。先行する取り組みを自分たちの目と身体で感じながら、利島の移住・定住促進施策へと還元していくことを目的に実施されました。
DAY1:裏砂漠とジオノスから学ぶ、「自然をまなざす視点」のつくりかた
圧倒的なスケールを前に、「島で暮らすこと」を問い直す—裏砂漠
初日は、伊豆大島ジオパーク認定ガイド・神田さんの案内で、大島を代表するジオサイト「裏砂漠」へ。
利島の方々にとって大島は、船の乗り継ぎで立ち寄る「経由地」であることが多く、島に滞在してじっくり歩く機会は意外にも多くありません。そこであえて、最初の訪問地を“観光名所”ではなく、火山島のダイナミックさを全身で感じられる場所に設定しました。

眼前に広がる黒い砂礫の斜面、容赦なく吹きつける風。
そのスケールに圧倒されながらも、参加者のみなさんは「島で暮らす」ことの土台にある自然環境の厳しさと豊かさを、あらためて身体で受け止めている様子でした。
利島でも、海や山、椿林などの豊かな自然は暮らしと切り離せない存在です。裏砂漠での体験は、「自然をどう楽しむか」だけでなく、「どう敬い、どう伝えていくか」というまなざしを、視察の最初にセットする時間になりました。
火山の島の“物語”をデザインする—伊豆大島ミュージアム ジオノス

続いて訪れたのは、2025年7月にリニューアルオープンした「伊豆大島ミュージアム – ジオノス」。大島町役場観光課の池田さんに、展示のコンセプトや運営の工夫などを丁寧にご案内いただきました。
プロジェクションVRシアターの4面スクリーンに包まれる没入型の映像体験や、火山とともに生きてきた人々の暮らしを、丁寧に編集して伝える展示構成。
ただ「情報を並べる」のではなく、「島を好きになる入口」をいくつも用意していることが印象的でした。

利島でも、椿や漁業をはじめとした産業や、学校、サークル活動など、暮らしの中に多くの物語が眠っています。
今回の訪問を通じて、「利島の資源や暮らしをどう編集し、来訪者や移住希望者に届けるのか」という“見せ方・伝え方”のヒントを、多く持ち帰ることができました。『ずっとしま』や今後の施設内展示を考えるうえでも、大きなインスピレーションになりそうです。
DAY2:WELAGOと椿の体験、そして「san-bashi」—拠点と関係性のデザインを学ぶ
自然共生×コワーキングという実験場—Izu-Oshima Co-Working Lab WELAGO
2日目は、複合型サテライトオフィスの先行事例として、伊豆大島のコワーキングスペース「WELAGO」を訪問しました。運営主担当の株式会社フロンティアコンサルティング・大前さんより、施設紹介に加え、これまでの試行錯誤や今後の展望についてお話を伺いました。

WELAGOは2025年、「自然共生サイト」の認定を受けたことをきっかけに、生態系のモニタリングや自然環境と共生するワークスタイルの実験拠点としての役割を強めつつあります。
「働く場所」としての利便性にとどまらず、島の自然と人の活動が折り重なる“ラボ”として、さまざまなプロジェクトが生まれていることが印象的でした。
利島で計画中の複合型サテライトオフィスも、「遊ぶ・学ぶ・働く・育む・つながる」を束ねたウェルビーイングラボとして構想が進められています。
WELAGOの実践は、
- コワーキングとコミュニティスペースをどう運用するか
- 自然共生や環境配慮という視点を、日々のプログラムや利用ルールにどう落とし込むか
といった具体的なイメージを持つうえで、非常に参考になる時間となりました。
椿とあそぶ、椿で暮らす—KARARAのワークショップと事業者訪問
その後、「KARARA – 椿とあそぶアトリエ」の杉本さんによるウッドバーニングのワークショップを体験。椿の木を丁寧に磨き、電熱ペンで思い思いに線を刻んでいきます。

同じ「椿」という素材を前にしながらも、参加者それぞれの個性がにじむ作品が並び、「椿との関わり方は、こんなにも多様になり得るのか」という気づきにつながりました。
この後に訪れた椿油製造業者さんや、椿オイルを活用したアスリートアロマトレーナー・高田さんのお話からも、椿が「商品」や「産業」を越えて、人の健康や暮らしの質、ウェルビーイングにまで広がっていく可能性を感じられました。

椿は、利島にとっても島の象徴であり、重要な産業でもあります。
「椿を“作る・売る”だけでなく、“体験する・ケアする・語り合う”場としてどう育てていくか」という問いは、利島の移住・定住においても大きなテーマになっていきそうです。
島と島、島と都市をつなぐ“桟橋”—Meetup「san-bashi #7 “ずっとしま”編」
夜は、WELAGOを会場に開催された東京諸島好きが集まるMeetup「san-bashi #7 “ずっとしま”編」に合流。

利島からは、地域おこし協力隊の小抜さん・石井さんが登壇し、利島での暮らしや現在取り組んでいるプロジェクト、『ずっとしま』の構想などをプレゼンテーションしました。
当日は、大島側から予定していた地域おこし協力隊の登壇が体調不良で叶わなかった一方で、大画面空間共有システム「tonari」を通じて東京・大手町とつながり、武蔵野美術大学の学生によるマップ型エッセイ「伊豆大島、情緒の旅」の完成報告も行われました。
プレゼン後の交流タイムでは、参加者同士が思い思いに会話を交わしながら、「大島と利島」「島と都市」「住んでいる人と関わりたい人」といった、さまざまな境界線を越えていく対話が自然と生まれていました。

利島の複合型サテライトオフィス構想でも、「関係人口の窓口」としての役割が重視されています。
今回のsan-bashiでの経験は、拠点を“出会いの桟橋”として運営していく際のヒント
- 島側からどのようなプロジェクトを持ち込むと、関わりしろが生まれるのか
- どのように外部のプレイヤーと協働していくのか
を考えるうえで、貴重な実践の場となりました。
DAY3:波浮港で想像した、「集落まるごとで迎える」未来
最終日は、伊豆大島の最南端・波浮港地区を散策しました。
ここでは、波浮港出身でゲストハウスや商店を営み、近年クラフトビールづくりにも挑戦している吉本さんに、地区の歴史や最近の動きについてお話を伺いました。

波浮の集落規模は、利島の集落とほぼ同じくらいと言われています。
その中で、個性的なゲストハウスやカフェが点在しながら、地区全体としてゆるやかに連携し、来訪者を受け入れている様子は、「島のサイズ感が近いからこそ、自分たちの未来の姿としてイメージしやすい」と参加者からも声が上がりました。
話題は、イタリア発祥の「街全体を一つのホテルと見立てる」分散型宿泊施設「アルベルゴ・ディフーゾ」の考え方にも及びます。
利島でも、一つの大きな施設にすべてを集約するのではなく、既存の住宅や空き家、公共施設を活かしながら、集落全体で移住希望者や来島者を迎え入れるような仕組みがあり得るのではないか。

波浮港での対話は、「施設整備」と「集落のあり方」をセットで考える重要性を、あらためて浮かび上がらせてくれました。
視察を通じて見えてきた、利島の移住・定住に向けたいくつかのヒント
3日間を通して浮かび上がってきたキーワードや方向性を、あえてラフなままいくつか挙げてみます。
- 自然をどう「入口」にするか
裏砂漠やジオノスで体感したような、自然と暮らしの関係性をまるごと伝える仕掛けは、利島における「ふらっと訪れる人」の入口づくりにも通じそうです。 - 拠点=ウェルビーイングラボという視点
WELAGOの取り組みや、ウェルビーイングに関する知見を踏まえると、単に用途の詰め合わせとして施設を設計するのではなく、「個人」「関係」「コミュニティと公共」の3つが同時に満たされる状態をどうつくるかが重要だと感じました。 - 椿とともにある暮らしの拡張
KARARAのクラフト体験や椿オイルをめぐる実践から、椿が「産業」だけでなく、「学び」「ケア」「表現」を生む媒介にもなり得ることを再確認しました。利島ならではの椿との付き合い方を、さらに掘り下げていけそうです。 - “関係をつくる場”としてのイベント運営
san-bashiのようなMeetupは、一度きりのイベントではなく、継続的に関係性を積み重ねていく装置として機能しています。利島の拠点でも、小さな実験や発表の場を日常的に組み込んでいくことが、移住・定住の土壌づくりにつながりそうです。 - 集落まるごとで迎える宿泊・暮らしのイメージ
波浮港での対話からは、拠点単体ではなく、集落全体を含めて移住希望者や関係人口の受け皿をデザインするという発想の重要性をあらためて感じました。

波浮港から利島を望む
「視察して終わり」にしないために—これからのアクション
今回の大島視察は、単に「良い事例を見て学ぶ」ことが目的ではありませんでした。
むしろ、「利島の暮らしとこれから」に引き寄せながら、どんな問いを持ち帰り、どんな小さな一歩から試していくのか -その種を見つける旅だったように思います。

今後は、『ずっとしま』編集部や地域おこし協力隊、役場のみなさんとともに、今回の視察で得た気づきやヒントをもとに、
- 複合型サテライトオフィスの具体的な運用イメージづくり
- 島内外のプレイヤーと連携したプログラムの企画
- ウェルビーイングラボとしての実験と、その記録・発信
などに少しずつ落とし込んでいく予定です。
変化は、きっと一気には訪れません。
それでも、波の間を縫うように、ゆっくりと芽吹く変化を信じながら——
利島の新たな移住・定住のかたちを、島のみなさんとともに育てていけたらと思います。
Let's Share
この記事をシェアするRelated articles
関連記事
あなたと大島との最適な関係性の探究をサポートする滞在企画『暮らし探究』について
在りたい生き方から島での暮らしを考えよう!あなたと大島との最適な関係性の探究をサポートする滞在企画『暮らし探究』を2月18日・19日の1泊2日の行程にて実施しま・・・
2023/01/14

「わたしの半福半X」公開プレゼンテーション&トークセッション開催
伊豆大島に入って福祉の現場や島で活動されている人たちと語り合いながら、自分らしい暮らし方や働き方を探す旅を通じて見つけたそれぞれの「わたしの半福半X」。9月10・・・
2023/09/03